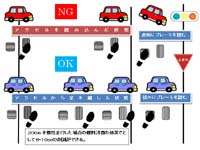プログラマー募集中。環境問題の解決に協力していただけませんか?
エコライフ楽しんでいきましょう!
いろいろな形のエコライフ、選びたいほうだいです。みなさんのエコライフを応援します。

おしらせ
2024年3月14日
自転車発電装置レンタル料 価格変更のお知らせ
2023年11月28日
ゼロカーボンで事業を行います
2023年4月3日
エコライフAIチャット
2023年2月1日
クルポアプリ公開(静岡県)
2022年4月12日
家電診断ツール2022年度に更新しました
2022年4月10日
「家庭CO2コントロールパネル」公開
エコライフのためにご活用ください
自転車発電イベントの紹介
2024年3月14日
自転車発電装置レンタル料 価格変更のお知らせ
2023年12月5日
文化祭「チャリ発電」で探究学習 品川女子学院中等部1年E組様
2022年6月19日
自転車発電 芸術祭で発電!?SOCIAL ENERGYの自転車発電ワークショップ
有限会社ひのでやエコライフ研究所
〒604-8874 京都市中京区壬生天池町27-4
電話 075-708-8152
E-mail: hinodeya@hinodeya-ecolife.com
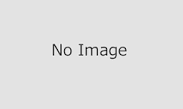

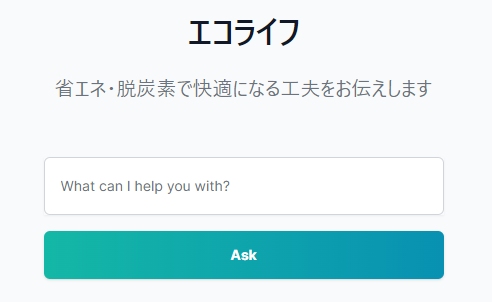

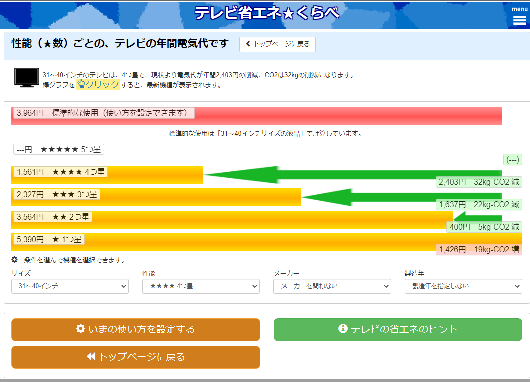

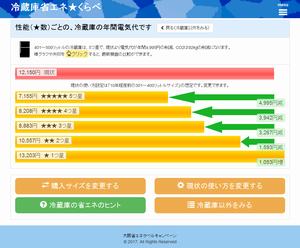
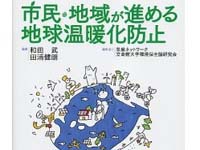

.jpg)